は使い方を守れば怖くない.jpg)
刈払機(草刈機)は正しい使い方さえ守っていれば怖いものではありません。
刃が回転することでどんな危険が生じるのかという点を中心に
刈払機(草刈機)の使い方のポイントをまとめました。
刈払機(草刈機)の使い方ポイントその1.作業を始める前
刈払機(草刈機)本体の点検と作業場所の安全確保がおもなポイントです。
1)作業前点検
作業前に刈払機(草刈機)の各部の点検を行います。
特にチップソーの回転軸部のゆるみ、刃の欠損等については念入りな確認が欠かせません。
2)作業場所の確保
作業エリアでの動線を想定し、障害となるものは取り除いておきます。
電源コードタイプの刈払機(草刈機)の場合は、
コードの取り回しも想定して、作業中に足を引っかけることがないようにしましょう。
刈払機(草刈機)使い方ポイントその2.作業中
いずれも「安全第一」の理にかなったものばかりです。
1)立ち入り禁止
作業中は他の人を近づけないようにします。
刈払機(草刈機)の回転刃だけではなく、刈られて飛び散る物も危険です。
ほとんどの刈払機(草刈機)では「半径15メートル以内は立ち入り禁止」として使い方の指定がされています。
2)騒音中は目で確認
特にエンジン式刈払機(草刈機)の場合は、操作中の騒音が大きいことから他の音が耳に届きません。
単調な動作の繰り返しですから地面ばかりに目をやりがちになります。
意識して顔をあげ、周りの状況を確認するようにしましょう。
3)作業者には前から近づく
上と同様の理由で、刈払機(草刈機)作業者に近づく場合は視界に入る正面からにします。
あるいは、よく響く笛などを用意しておくのもよいでしょう。
4)刈払機(草刈機)の点検はスイッチを切ってから
刈った草やロープ等の廃棄物が絡まった場合、回転が止まることがあります。
それは抵抗がかかって止まっているだけであって、刈払機自体は動作を続けています。
油断してそのまま除去してしまうと、とたんに回転が再開されて危険です。
刈払機(草刈機)の回転が止まった時は必ずスイッチを切ってから点検しましょう。
5)刃先の確認
朽木の根元など硬い障害物に当たった場合は、いったんスイッチを切って刃の状態を確認します。
「何かあったらまず刈払機(草刈機)の動作を止める」これが使い方の大原則です。
刈払機(草刈機)使い方ポイントその3.操作の要領
回転刃のクセを知っておくと効率良い使い方ができます。
1)腰を中心に
腕で刈払機(草刈機)を左右に振るのではなく、
どちらかというと上半身の体制は変えずに、腰を軸にして円弧の要領で動くことをイメージします。
足の運びと腰の回転を一連の動作にして、リズムをつけて反復することが作業を楽にするためのコツです。
2)右から左に
刈る方向は右から左に。
これは刈刃が反時計回り(左回り)に回転することによるものです。
こうすることで刈られた草が左側に集められて、次の動作の際に足場が確保できるようになります。
3)2回に分けて刈る
通常は草の根元を刈りこんでいきますが、背丈の高い茂みでは地面にどのような障害物があるのかが分かりません。
最初から下を狙うのではなく、いったん途中部分で刈って視界を確認します(二段刈り)。
4)跳ね返りに注意
刈払機(草刈機)の回転中の刃は、位置によって特性が異なります。
左回りですから、右側前半部に障害物が接触すると、
回転する力がまともにぶつかって跳ね返ってしまう(キックバック)恐れがあります。
「慣れ」も恐ろしい
バッテリー式の軽量タイプも登場したことで、刈払機(草刈機)は一般の家庭でも気軽に使われるようになりました。
けれども、鋭い刃が高速で回転する危険なものであることには変わりありません。
よく「作業中の事故は終了時に起きやすい」といわれますが、
刈払機(草刈機)の使い方に慣れたら慣れたで気の緩みからくる別の危険が生まれたりもします。
刈払機(草刈機)に限らず、どんな機械でも基本中の基本ですが、いちどは取扱説明書に目を通しましょう。
便利な刈払機(草刈機)をどんどん活用しましょう
刈払機(草刈機)は製品のクセ(特に刃の回転についての特性)を押さえてさえいれば、とても便利な道具です。
必要以上に恐れず正しい使い方を守って、どうぞ積極的に活用してください。
ポイントは、まずは作業の用途を見極めること。
それに合った機種を選べば間違いありません。
ボクらの農業でも刈払機(草刈機)のラインアップは豊富です。
迷ったときはどうぞご相談ください。商品選びのお手伝いをさせていただきます。
▼草刈機の選び方ページをリニューアルしました!読み物はより読みやすく、絞り込み検索はそのままです。ぜひ見てみてください▼
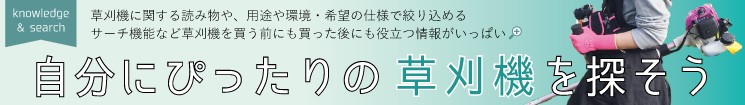











この記事にご満足いただけましたら、ぜひこちらのボタンからシェアをお願いします!